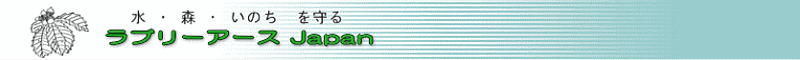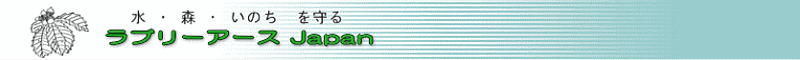| バックナンバー |
 |
森のひとり言
|
 |
|
森のひとり言・New
|
|
※このコーナーは、みなさんのご質問やご意見をもとに執筆されています。どんなことでも、お待ちしています。
こちら からどうぞ。
|
|
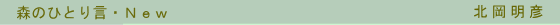 |
その壱百拾四 : 新しい年に想う、森の大切さ、楽しさ
この2月で69才になりますが、まだ体調も良く、山歩きができる体力が残っているのは幸いです。昨年は、年間で観察会や講演会などを、のべ212日こなすことができ、いろいろな花(もちろん野生植物)を765種類も楽しむことができました。なにしろ、体の健康が一番大切です。皆さんも、健康に気をつけて下さいね。
昨年、各地の植物を調査している際に感じたことがいくつかありますので、
ちょっとお話ししましょう。
まずは、植物相の変化です。
近年増加しているのが、ランの仲間です。暖帯性の種類に加え、腐生ラン(葉緑素を持たないで、地中の腐葉土から養分を得るランの仲間)が急増しています。前者の例がコクラン、後者の例がムヨウラン類やクロヤツシロランです。シカの食害により、地表付近が明るくなってきたことも影響しているかも知れません。もちろん、地球温暖化が、主な要因だと思われます。
次に、二次林(原生林を何度も利用伐採してきた後、植林しなかった森林)
の変化です。
コナラ・アベマキ・ヤマザクラを主とした二次林が林齢80年を越えて、老木化が進んできました。その林床は暗くなり、十分な光を必要とする、これらの樹種の幼木(次世代)は、全く育つことができません。育つのは、カシ類やヒサカキ・カクレミノなどの常緑広葉樹がほとんどです。所によっては、シイの幼木も、多く見られます。
こうした姿を、「森が荒れている」と表現することがありますが、それは、全く間違いです。単純に、人が手を加えなくなったため、自然の仕組みの中で最も重要な「植生遷移」が進んだだけなのです。植生遷移とは、800年程かけて、裸地から、その場所特有の原生林の成立まで変化していく自然現象です。ですから、何も気にすることはありません。
ただ、この地域の原生林は、ほとんどシイ−カシ林で一年中薄暗く、身近な森としては、快適といえない面もあります。ですから、快適性を求めて、森の手入れをすることが全て間違いということはありません。私たち人間の都合で、あくまで。
それにより、維持できる動植物もたくさんいます。でも、人間が手入れしなければ絶滅する種類が多いというのは間違いです。何といっても、全ての動植物が、私達人類より歴史が古いのですから。
こうした、自然と人間の関係をじっくり考えてみることは、とっても大切なことです。まずは、自然の素晴らしさを心から楽しみ、次に、どのようにして目の前の自然が成り立っているかを考え、最後に、私たちがこれからどのように自然とつきあえば良いかを、じっくり考えてみることが大切だと思います。
新ためて、年の始めに、そう思いました。
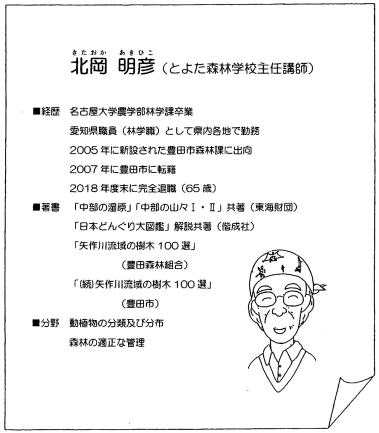
|
|
|
| (2023.01) |
|