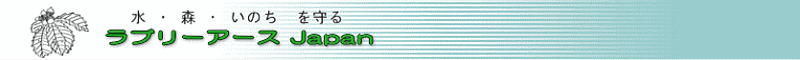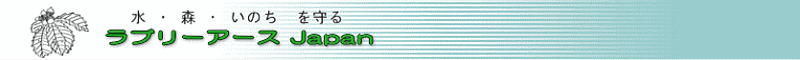| バックナンバー |
 |
森のひとり言
|
 |
|
森のひとり言・New
|
|
※このコーナーは、みなさんのご質問やご意見をもとに執筆されています。どんなことでも、お待ちしています。
こちら からどうぞ。
|
|
その壱百拾参 : 自然のしくみを楽しもう(6)
自然のしくみを理解していると、山歩きやウオーキングが本当に楽しくなります。「植生遷移」「植物の垂直分布と水平分布」に続き、今回は植物と動物の関係である「食物連鎖(しょくもつれんさ)」を紹介しましょう。
近年いろいろな新しい呼び名はありますが、ひとつの生態系の中で多くの動植物が関係して、それらが「食う―食われるの関係」で鎖のように、次々とつながっていることを「食物連鎖」と呼びます。
もちろん、出発点は、無機質である二酸化炭素CO2と水H2Oから太陽光エネルギーを使って有機物であるデンプンC6H12O6を作る葉緑素(クロロフィル)を持った植物です。これを生産者と呼びます。
この光合成能力を持たない動物の多くは、葉・幹・実などを直接食べる(植食性動物と呼ぶ)か、その植食性動物を食べ(肉食性動物と呼ぶ)、消費者と呼ばれます。
さらに、生産者や消費者の遺体を分解して、植物が根から吸収しやすくする役割を担う昆虫・土壌動物・菌類などを、分解者(還元者)と呼びます。
これらすべての動植物が互いに複雑に絡み合って、食物連鎖が成立します。
例えば、豊田市稲武町にある、面の木峠ブナ原生林における食物連鎖をごく簡略化すると、次の図のようになります。
クリックで拡大します
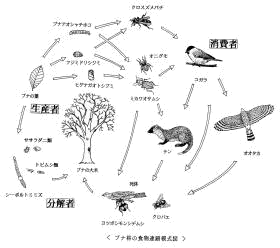 生産者であるブナの葉をブナアオシャチホコやフジミドリシジミなどいろいろな昆虫(主に幼虫) が食べ、これらを「第一次消費者」と呼びます。 生産者であるブナの葉をブナアオシャチホコやフジミドリシジミなどいろいろな昆虫(主に幼虫) が食べ、これらを「第一次消費者」と呼びます。
それらの幼虫や成虫をクモ類やハチ類といった動物たちが食べ、これらを「第二次消費者」と呼びます。
さらに、それらを「第三次消費者」であるコガラなどが餌として食べ、コガラを「第四次消費者」であるオオタカやテンが食べます。
そして、分解者であるシデムシやハエが動物の遺体や糞を、ササラダニ・トビムシ・ミミズなどが落ち葉を分解し、最終的にはバクテリアや菌類の働きにより、植物が吸収できるような状態まで分解されます。
超模式的に図化すればこうなりますが、実際には、そこに住むすべての生物が複雑に関わって食物連鎖が成りたちます。
一度、じっくり考えてみてください。
|
| (2021.04) |
北岡明彦さんを紹介します
1954年2月、名古屋市熱田区に生まれる。わずかに残る自然の中で「昆虫少年」として育つ。昆虫から植物、野鳥へと得意分野を広げながら、
日本全国を飛び回る。
名古屋大学農学部林学科卒。愛知県林務課を経て、現在豊田市森林課勤務。日本自然保護協会の自然観察指導員。フィールドでの活動を重視し、
一年中、 公私の観察会で活躍。動植物全般の博識と森林の専門家としての教唆には絶大な信頼がある。 その人柄にもひかれて 「北岡ワールド」に魅せられた人々は多い。
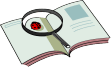 『中部の山々1,2』(東海財団)『日本どんぐり大図鑑』(偕成社)など執筆、編集。「面の木倶楽部」 「瀬戸自然の会」を主宰。愛知県瀬戸市在住。
『中部の山々1,2』(東海財団)『日本どんぐり大図鑑』(偕成社)など執筆、編集。「面の木倶楽部」 「瀬戸自然の会」を主宰。愛知県瀬戸市在住。 |
|